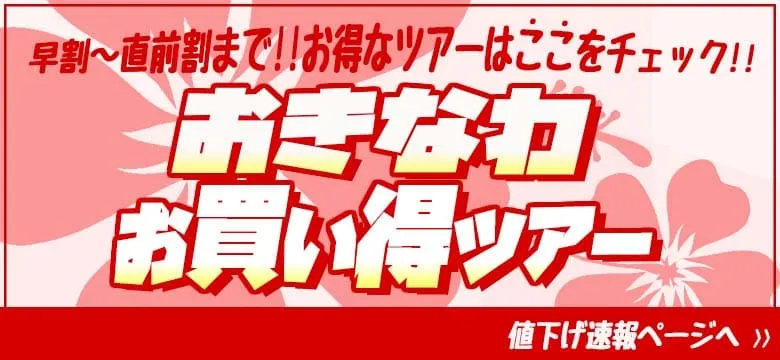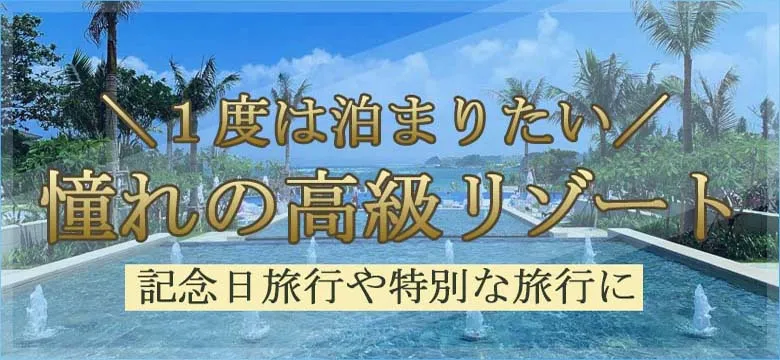-
2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( イベント )
やんばるで1日中遊ぼう! FOREST MARKET
自然の中で1日中楽しめるイベント
5月6日(土)、沖縄北部の本部町で1日中楽しめる野外イベントの「フォレストマーケット」が開催される。フォレストマーケットは年に2回開催されていて今回は12回目。
豊かな自然の中に並んだ様々な店のテントで買い物をしたり、ピクニックをしたりして、野外ならではの楽しみ方ができるイベントだ。
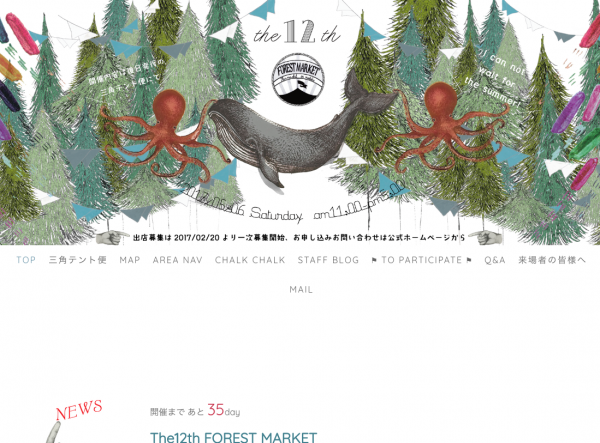
店舗は複数のエリアに分かれている
会場となるのは本部町八重岳さくらの森公園。マーケットは、この公園内の複数のエリアに分かれて開かれる。
エリアは大きく分けて、商品や食べ物を販売するエリア、パフォーマンスエリア、地面に自由に絵を描けるGRAFITTI エリア、ワークショップエリア、ピクニックスペースなどに分かれている。
商品販売エリアには、焼き菓子やご飯もの・ドリンク類が並ぶフードエリアの他に、手作り品が並ぶハンドメイドエリア、大切に使われてきた品物や新品の商品が並ぶフリーエリア、アンティークや古道具・ヴィンテージが並ぶヴィンテージエリアなどがある。
3月30日現在、販売エリアでは40店近くの出店が決定している。詳しい出店状況はホームページのスタッフブログから確認できる。また、前回の様子はFacebookから見ることができる。
開催概要
開催日時は5月6日(土)11:00~17:00。会場は八重岳さくらの森公園(沖縄県国頭郡本部町並里921)。野外開催のため荒天により中止される場合がある。
(画像は FOREST MARKET ホームページより)
外部リンク
FOREST MARKET
https://forestmarket-yanbaru.jimdo.com/Facebook The11th FOREST MARKET
https://www.facebook.com/
2017年5月6日、沖縄北部の本部町で1日中楽しめる野外イベントの「フォレストマーケット」が開催される。フォレストマーケットは年に2回開催されていて今回は12回目。豊かな自然の中に並んだ様々な店のテントで買い物をしたり、ピクニックをしたりして、野外ならではの楽しみ方ができるイベント。
-
2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( NEWS )
知らなかった!沖縄が1番なこと!!
様々なものやことが統計処理されるようになって、ありとあらゆるランキングが公表されています。沖縄が1位というのは何だろう?ふと気になって調べてみました。
データは「都道府県別統計とランキングで見る県民性 by odomon.net」を参考にさせていただきました。

納得の1番
気候関連
年間気温の全国平均は15.2度だそうです。沖縄県は23.1度で全国1位。以下、鹿児島、宮崎、長崎、福岡と九州各県が上位を独占。低いほうは北海道の8.9度。
真夏日の年間日数も沖縄が1番です。納得というより、そんなの当たり前だろうという結果でした。(気象庁の観測データより)
鉄道駅の数
鉄道の駅は全国に9,716あります(2007年)。人口10万人あたり7.60駅。沖縄県はモノレール駅が15あるだけなので、最も少ないほうの1番で1.10駅。最多は高知県の21.22駅です。(愛知県ホームページより)
在日アメリカ人
在日アメリカ人の総数は5.1万人(2015年6月現在)で日本の人口1万人あたり4.05人。最多は沖縄県の16.95人。以下、東京都、神奈川県と続きます。(法務省の在留外国人統計より)
法務省の統計には米軍とその家族は含まれていないので、これらを加えるともっと多くなります。
ベーコン消費量
1世帯あたりのベーコン消費量は全国平均で1,479グラム。沖縄県は2,152グラムで全国1位。以下、北海道、長崎県、秋田県と続きます。北と南が多いですね。(総務省の家計調査より)
死亡原因
脳梗塞の全国での死亡者数は69,967人。人口10万人あたり54.96人。沖縄県は最も少なくて28.83人。最も多いのは山形県で102.72人。胃がんによる死亡率も、最も低いのは沖縄県。さすが長寿のお国です。
凍死者のランキングというのもあります。全国の1年間の凍死者数は1,176.0人。人口100万人あたりだと9.25人。最も少ないのは沖縄県で2.11人。最も多いのは島根県で25.83人。
少ないほうの1番は納得ですが、沖縄で凍死する人がいるということが驚きです。(厚生労働省の人口動態統計より)
お寺、神社、教会
全国のお寺の数は77,467寺、人口10万人あたりだと60.75寺。神社は81,320社で同じく63.78社。キリスト教会は32,981教会で同じく5.62教会。
沖縄県は、お寺と神社は最も少なくて人口10万人あたりそれぞれ、5.57寺と0.94社。逆にキリスト教会は沖縄が最も多くて15.20教会。面白いですね。(文化庁の宗教年鑑より)
意外な1番
年間快晴日数
年間快晴日数の全国平均は28.4日。沖縄県はなんと最も少なくて8.9日。最も多いのは埼玉県(熊谷市)で58.6日。沖縄といえば、真っ青な海と空というイメージがあるので意外です。(各都道府県のデータを相加平均)
プロ野球選手出身地
人口10万人あたりのプロ野球選手の数は全国平均で0.63人。最も多いのは沖縄県で1.90人です。以下、福井県、佐賀県、大分県、と続きます。
選手の総数だと、大阪府(72人)、福岡県(54人)、神奈川県(53人)の順になるそうです。(サンケイスポーツ選手名鑑より)
飲み屋店舗数
意外な1番じゃなくて納得の1番だろう、という声が聞こえてきそうです。
全国にある飲み屋は233,101軒。20歳以上10万人あたりだと222.30軒。1番は沖縄県で、554.61軒。なんと全国平均の2.5倍。以下、宮崎県、青森県、高知県、北海道と続きます。
ベーコンの消費量と同じで上位は北と南に偏っています。(総務省の経済センサス‐基礎調査より)
離婚率
離婚が最も多いのは沖縄県で、夫婦100組あたり1.28件以下、大阪府、沖縄県、東京都、宮崎県と続きます。最も離婚が少ないのは新潟県で0.54件。(厚生労働省の人口動態調査より)
書道教室数
全国の書道教室は10,222軒で、人口10万人あたり軒数は8.04軒。最も書道教室が多いのは沖縄県で17.24軒。
だから何だ、と言われると困るのですが、とにかく沖縄が1番なのです。(総務省の経済センサス‐基礎調査より)
まとめ
何でも順位をつければよいというものではないと思いますが、順に並べてみると意外な事実に気づくことがあります。今度、ご自分の都道府県のランキングを調べてみると面白いかもしれません。
(画像は写真ACより)
様々なものやことが統計処理されるようになって、ありとあらゆるランキングが公表されています。沖縄が1位というのは何だろう?ふと気になって調べてみました。
-
2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( おすすめ情報 )
沖縄で思い出作り!沖縄の伝統⼯芸と体験できるスポット︕
沖縄旅行で皆さんはどんな計画を立てますか。マリンスポーツ、美ら海水族館、首里城など歴史探訪、沖縄料理食べ尽くし、島巡り、エイサーなど伝統行事などいろいろありますね。でも、もうひとつあります。工芸体験です。
沖縄には陶器、機織り、ガラス、染め物など体験できる伝統工芸がいろいろとあります。そして、こうした体験工房が一堂に集まった体験型テーマパークがあるのです。
沖縄の伝統工芸と、体験型テーマパークについて調べてみたのでご紹介しましょう。

沖縄の伝統工芸
壺屋焼
壺屋焼(つぼややき)は沖縄を代表する焼き物。那覇の壺屋地区が主な産地であることからこの名がつきました。
「荒焼(アラヤチ)」と「上焼(ジョーヤチ)」に分けられ、荒焼は南蛮焼で、釉薬なしが多く、酒甕、水甕、味噌甕など大型の焼き物。「上焼」は釉薬を施し、食器、酒器、花器類などが作られています。
琉球ガラス
琉球ガラスは、沖縄独特の吹きガラス工芸です。吹きガラスは、明治の頃、大阪や長崎から伝わったといわれています。厚みのある形や気泡が素朴な味わいとなって、沖縄独自のガラスが生まれました。
首里織
琉球王国は、東南アジアや中国との交易で織物の技術を学び、沖縄の気候風土のなかで、多様な琉球織物を生み出してきました。
特に王府首里では、王族、貴族、士族のために、格調の高い麗美な織物が生まれました。「首里織」という名称は、昭和58年の通産省伝統産業法指定申請の際に命名されましたものです。
紅型
紅型(びんがた)とは、沖縄を代表する伝統的な染色技法です。「紅」は色を、「型」は模様をさしているいわれています。古くからの東南アジア等との交易により、インドやジャワの技法を取り入れて、沖縄独自の染め物として発達してきました。
琉球漆器
沖縄では古来、中国漆器の技法習得に務め、そして漆器の生産に力を入れてきました。生産された漆器は中国風で、将軍家への献上品にも用いられました。朱塗りの美しさと黒塗りとのコントラストが琉球漆器の特長となっています。
体験型テーマパーク
むら咲むら
住所:沖縄県中頭郡読谷村字高志保1020-1
電話:098-958-1111
アクセス:那覇バスターミナルから路線番号28番線バス乗車。読谷村(よみたんそん)大当(うふどー)バス停下車、徒歩約10分。
HP:http://murasakimura.com/
琉球村
住所:沖縄県国頭郡恩納村山田1130
電話:098-965-1234
アクセス:那覇空港から車で国道58号線を北へ30km、約60分。
HP:https://www.ryukyumura.co.jp/official/
那覇市伝統工芸館
住所:沖縄県那覇市牧志3-2-10 てんぶす那覇
電話:098-868-7866
アクセス:牧志駅(那覇空港から16分)下車徒歩4分
HP:http://kogeikan.jp/index.html
琉球ガラス村
住所:沖縄県糸満市字福地169番地
電話:098-997-4784
アクセス:那覇空港から車で約25分。ひめゆりの塔すぐ近く。
HP:http://www.ryukyu-glass.co.jp/
シーサーパーク 琉球窯
住所:沖縄県名護市為又479-5
電話:0980-43-8660
アクセス:
HP:http://taiken-jp.net/ryukyu/
沖縄工芸村
住所:沖縄県国頭郡恩納村字恩納6203-1
電話:098-966-2910
アクセス:那覇空港より(国道)約70分
HP:http://www.okinawa-kougeimura.com/
体験工房 美ら風
住所:沖縄県那覇市牧志3-6-44
電話:098-866-8558
アクセス:ゆいレール 美栄橋、牧志駅下車、国際通り経由で徒歩8分。
HP:http://taiken-jp.net/churak/
まとめ
工芸体験にはまるとこれだけで沖縄旅行の日程を使い果たしてしまうかもしれません。他の見所もたくさんあるので、日程のやりくりの悩みがまた一つ増えてしまいますが、きっといい思い出になること請け合いです。
(画像は写真ACより)
沖縄旅行で皆さんはどんな計画を立てますか。マリンスポーツ、美ら海水族館、首里城など歴史探訪、沖縄料理食べ尽くし、島巡り、エイサーなど伝統行事などいろいろありますね。でも、もうひとつあります。工芸体験です。沖縄には陶器、機織り、ガラス、染め物など体験できる伝統工芸がいろいろとあります。そして、こうした体験工房が一堂に集まった体験型テーマパークがあるのです。沖縄の伝統工芸と、体験型テーマパークについて調べてみたのでご紹介しましょう。
-
2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( イベント )
うるま市で第15回 「もずくの日」イベント 那覇でも
4月の第3日曜日は「もずくの日」
「もずく」は古くから全国各地で食用にされてきた海藻の仲間であるが、国内で産業的規模の養殖が成功したのは、沖縄だけである。昭和54年のもずく養殖業の定着以来、養殖技術の向上で生産力が高まり、99%以上のシェアを占めるに至った。
「もずくの日」は、生産・流通に携わる沖縄の業者が、もずくのPRのために、平成14年に制定したものである。「もずくの日」とされた4月の第3日曜日には、もずく産業振興の一環として、旬のもずくを見て、触れて、食べてもらい、消費者に親しんでもらうイベントが、関連業者により毎年開催されている。

イベント基本情報
開催日時は、平成29年4月16日(日)、10:00~17:00、開催場所は、うるま市勝連平敷屋漁港で、漁港にある勝連漁業協同組合の住所は沖縄県うるま市勝連平敷屋3821-18となっている。
イベントでは、景品のもらえる「もずく早食い大会」や「もずくクイズ大会」を始め、「もずく漁場見学」や「もずくつかみ取り」などのもずく体験コーナー、さらに漁協によるもずく商品・加工品の販売が予定されている。
勝連漁業協同組合、沖縄県もずく養殖業振興協議会が主催、沖縄県農林水産部、うるま市が後援している。問い合わせ先は勝連漁協で、電話は098-983-0003である。
また、同日11:00~17:00に、那覇市てんぶす館前ポケットパークにて、同様のイベントが開催される。こちらの会場住所は、沖縄県那覇市牧志3丁目2番10号である。なお、市街地であるため、「もずく漁場見学」などの体験コーナーはなく、代わりにライブがプログラムに入っている。
会場アクセス情報
勝連漁業協同組合へは、那覇の「バスターミナル前」発の路線バス27番系統で「平敷屋」バス停まで乗車、そこから徒歩12分である。
那覇市てんぶす館へは、那覇市内の路線バスを利用し、「てんぶす前」停留所で下車、もしくはゆいレール「牧志」駅から450m、徒歩6分でもよい。
(画像は沖縄県もずく養殖業振興協議会ホームページより)
外部リンク
2017年 第15回「もずくの日」イベント(うるま市勝連平敷屋漁港)
http://www.mozukukyo.org/?p=17102017年4月の第3日曜日は〇〇〇の日!!
http://www.mozukukyo.org/?p=1715
「もずく」は古くから全国各地で食用にされてきた海藻の仲間であるが、国内で産業的規模の養殖が成功したのは、沖縄だけである。昭和54年のもずく養殖業の定着以来、養殖技術の向上で生産力が高まり、99%以上のシェアを占めるに至った。「もずくの日」は、生産・流通に携わる沖縄の業者が、もずくのPRのために、平成14年に制定したものである。「もずくの日」とされた4月の第3日曜日には、もずく産業振興の一環として、旬のもずくを見て、触れて、食べてもらい、消費者に親しんでもらうイベント。
-
2022/05/14沖縄旅行:カテゴリ( イベント )
沖縄県立博物館・美術館が5月27日に無料開放とイベント
「国際博物館の日」にあわせて無料開放やイベント
沖縄県立博物館・美術館では、「国際博物館の日」にあわせて5月27日に無料開放とイベントを実施する。

「国際博物館の日」は、博物館や美術館の活動を広くアピールするためにICOM(国際博物館会議)によって5月18日と定められた。そのため、全国の博物館や美術館でこの日にあわせて様々な取り組みが行われている。
この日に無料で見学できるのは「博物館常設展」と「美術館コレクション展」の展示室。企画展や特別展は有料となる。開館時間は9:00から20:00で、最終入館は19:30。当日は駐車場が満車になる可能性があり、できるだけ公共交通機関を利用するように呼びかけられている。
博物館・美術館の裏側を案内するツアーや展示解説も
博物館では、博物館の裏側を学芸員が案内する「バックヤードツアー」、常設展の美術工芸部門を中心に担当学芸員が約1時間の「展示解説会」、博物館ボランティアガイドにより常設展のみどころや楽しむポイントなどを伝える展示ガイドが行われる。
美術館では、前半は美術館の裏側を案内し後半は展示室で話をしながらの作品鑑賞を楽しむ「ミュージアムツアー」、コレクションギャラリーで開催中の「安次富長昭展-光・風・土の憧憬」を担当する学芸員による「作品解説会」を行う。
他にも、毎週土曜に行われている「ふれあい体験室ワークショップ」も実施する。
バックヤードツアーとミュージアムツアーはそれぞれ定員12名であり、申し込みが必要となる。解説会は2館ともに定員はなく、参加者は当日来館することとなっている。申し込み方法やイベントの詳細は公式ホームページで確認を。
(画像は沖縄県立博物館・美術館より)
沖縄県立博物館・美術館では、「国際博物館の日」にあわせて2017年5月27日に無料開放とイベントを実施する。「国際博物館の日」は、博物館や美術館の活動を広くアピールするためにICOM(国際博物館会議)によって5月18日と定められた。そのため、全国の博物館や美術館でこの日にあわせて様々な取り組みが行われている。
-
2017年5月6日、沖縄北部の本部町で1日中楽しめる野外イベントの「フォレストマーケット」が開催される。フォレストマーケットは年に2回開催されていて今回は12回目。豊かな自然の中に並んだ様々な店のテントで買い物をしたり、ピクニックをしたりして、野外ならではの楽しみ方ができるイベント。
-
様々なものやことが統計処理されるようになって、ありとあらゆるランキングが公表されています。沖縄が1位というのは何だろう?ふと気になって調べてみました。
-
沖縄旅行で皆さんはどんな計画を立てますか。マリンスポーツ、美ら海水族館、首里城など歴史探訪、沖縄料理食べ尽くし、島巡り、エイサーなど伝統行事などいろいろありますね。でも、もうひとつあります。工芸体験です。沖縄には陶器、機織り、ガラス、染め物など体験できる伝統工芸がいろいろとあります。そして、こうした体験工房が一堂に集まった体験型テーマパークがあるのです。沖縄の伝統工芸と、体験型テーマパークについて調べてみたのでご紹介しましょう。
-
「もずく」は古くから全国各地で食用にされてきた海藻の仲間であるが、国内で産業的規模の養殖が成功したのは、沖縄だけである。昭和54年のもずく養殖業の定着以来、養殖技術の向上で生産力が高まり、99%以上のシェアを占めるに至った。「もずくの日」は、生産・流通に携わる沖縄の業者が、もずくのPRのために、平成14年に制定したものである。「もずくの日」とされた4月の第3日曜日には、もずく産業振興の一環として、旬のもずくを見て、触れて、食べてもらい、消費者に親しんでもらうイベント。
-
沖縄県立博物館・美術館では、「国際博物館の日」にあわせて2017年5月27日に無料開放とイベントを実施する。「国際博物館の日」は、博物館や美術館の活動を広くアピールするためにICOM(国際博物館会議)によって5月18日と定められた。そのため、全国の博物館や美術館でこの日にあわせて様々な取り組みが行われている。